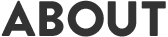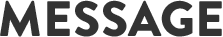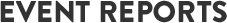総文の行方
茂 牧人
ホモ・サケルと真の公共性
さらにいえば、その超越の次元は、その公共性や複数性から除外され、はみ出したホモ・サケル(アガンベン)の様な存在者の犠牲が必要になってくるということで締めくくりたいと思っています。というのは、この総合文化政策学部にいる私たちは、自分の実力でこの場を占めていると考えられるでしょうか。私は、それはかなり傲慢な考えだと思います。やはり根本的に、「なぜ私がここにいるのか」「なぜ私が総合文化政策学部の一員なのか」という問いに対しては、全くの偶然性が伴っていると思います。根本的に、私でなくてもよかったのに、今私がここにいるという偶然性がつきまといます。しかし同時に、その偶然性をつきつめるときに、ある種の必然性を感じるのです。「ここにいるのは、何らかの必然性(神の摂理)があってここにいる」と。このような偶然性と必然性との結合は、いったいどこからくるのかということを考えるときに、公共性から除外された人の犠牲が、必要となってくるのです。
大澤氏が一つのエピソードを出しています。阪神淡路大震災があったときに、ある女性が、1995年1月17日の朝10分だけ早く起きた。そのために自分は、家具の下敷きにならなくて済んだが、夫は、家具の下敷きになって死んでしまった。その後彼女は、「なぜ私が助かって、夫が死ななければならなかったのか」という自分自身の存在の偶然性に苦しんだというのです。また、この問いは、アウシュビッツを生き延びたユダヤ人の間でよく問われるものでもあります。「なぜ私が、生き延びたのか」。それで多くのユダヤ人が苦しんでいたのでした。
私たちの存在の中には、根源的に偶然性が潜んでいます。そして、それは、他者の死の犠性の上に成り立っているということです。なぜ私が、亡くなった彼/彼女でなかったのか、と。そのような感覚をヤスパースは、「形而上的な罪責」と言っています。つまり、私の存在の中に、予め根本的に他者の犠牲が潜んでいるのではないか。他者の犠性が、アプリオリに根本的に私の中に含まれているのではないか。それを表現したのが、キリストの十字架の受難と死と復活ではないかというのです。
そこでは、神という超越者が、自ら人間となり、その神であり人間である方が、自ら犠牲となるということです。絶対性をもった超越者が自己否定するということで、私どもに代わって受難と死を引き受けてくれたのであり、絶対者が自己否定をして、苦難を受けることで、私どもが苦難を生きているということとの共鳴が生まれてくるのです。この絶対者が、公共性から排除されて(馬小屋で生まれ、十字架にかかる)、自ら自己犠牲となることがあって、その出来事と私どもの苦難が共鳴するということです。
そのような出来事が中心にあるときに、真の自由の公共性と複数性が成立してくると考えられるのです。それはただ単なる普遍性を言い表す公共性や複数性ではなく、ある種の逆説的な公共性であり、複数性であると言えるでしょう。そのような逆説的公共的空間の中にこそ、真の公共性が生まれてくるように思います。